生のなかば ヘルダーリン詩学にまつわる試論 (叢書・エクリチュールの冒険)
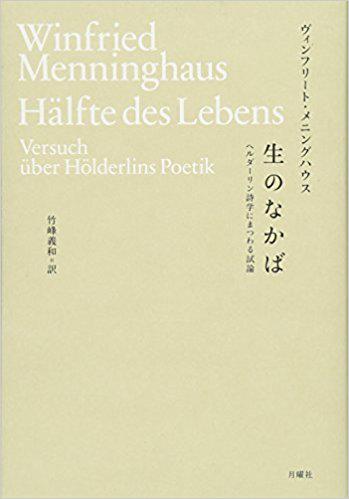
ヘルダーリンの抒情詩『生のなかば』は、この詩人が遺した膨大な数の詩作品のなかでもっともよく知られている。ヘルダーリンの詩集にはほとんど必ずこの作品が収録されており、付曲の試みも枚挙に暇のないほどだ。もっとも、この詩をめぐる解釈は、ほぼ例外なくひとつのパターンに従ってきた。すなわち、「生のなかば」=中年に達した語り手である「私」が、若い前半生の輝きを追想する一方、迫りくる後半生の寂寞を予感するさまを歌っているというものである。そこにさらに、この詩を執筆してからほどなくして狂気に陥り、後半生をつうじて療養生活を余儀なくされたヘルダーリン自身の悲劇的な生涯の予兆を読み込むような解釈も付け加わったりもするが、それもまた、この「ミッドライフ・クライシス」の類型のヴァリエーションの範囲にとどまっていると言える。
それにたいして、本書においてメニングハウスが試みるのは、『生のなかば』をめぐる従来的な解釈パターンには収まらない、まったく新たな読みの可能性を示すことである。そして、その際にもちいられるのが韻律分析という古典文献学的な手法にほかならない。通常は自由韻律詩というカテゴリーに区分されている『生のなかば』にたいしてメニングハウスは、ある大胆な仮説を呈示する。すなわち、表題(“Hälfte des Lebens“〔生のなかば〕)から最終詩行(“Klirren die Fahnen.“〔風見が鳴りきしむ。〕)にいたるまで、この短詩のうちに執拗に回帰してくる「アドーニス格」と呼ばれる5音節(強弱弱強弱)をつうじて、ヘルダーリンは夭折の美少年アドーニスの神話を暗に召喚しているのではないかというのだ。さらに著者は、この「アドーニス格」が、古代ギリシアの女性抒情詩人サッポーに由来するサッポー詩型の終句をなすものであることから、サッポーにまつわるイマジュリーもこの詩のうちに寓意的なレヴェルで潜在しているという点を、圧倒的な文献学的知識と丁寧な論証によって明らかにしていく。
ただし、本書におけるメニングハウスの企図は、『生のなかば』を素材として「寓意的韻律論」を展開することだけにとどまらない。20世紀初頭にゲオルゲ派のヘリングラートによってヘルダーリンの後期のピンダロス風の詩作品が新たに〈発見〉されて以来、この詩人には、神々と人類を媒介する預言者としての詩人という男性的・英雄的なイメージがつねに付着してきた。ハイデガーやアドルノ、ソンディのヘルダーリン論も、もっぱら後期讃歌に着目することで、そのような〈ピンダロス化されたヘルダーリン〉の解釈伝統の枠組みを踏襲してきたと言えるだろう。だが、メニングハウスが『生のなかば』におけるアドーニスおよびサッポーという隠された形象に着目することで強調するのは、いささかマッチョなヘルダーリン像の影に隠れるかたちで完全に忘却されてきた、柔和にして女性的な抒情詩人としての側面である。ヘルダーリン自身が遺した詩論的なテクストでは、作品のなかで異なる音調を交替させるという詩的技法について綱領的に述べられていたが、『生のなかば』のみならず、後期讃歌においてすらもサッポー詩型に由来するアドーニス格が頻繁に登場するという事実は、ヘルダーリンの詩作品を男性的な契機と女性的な契機の交替として読み解く必要性を告げているのである。
古典的な文学研究が世界的に退潮傾向にあるなかで、詩作品の分析や韻律論にたいする学術的な関心がますます薄らいでいることは間違いない。その一方で、文学作品について論じられる場合でも、テクストそのものに正面から向き合うかわりに、ハイデガーやベンヤミン、アドルノ、さらにはドゥルーズ、デリダ、アガンベンといった著名な思想家たちの解釈をたんに敷衍することで満足するような安直な傾向が多分に見られるのではないかと、自戒の念とともに自問せざるをえない。テクストに密着し、韻律分析のような地味な作業を徹底することによってこそ、「哲学的」なアプローチだけでは到達しえないような解釈の地平が開かれるのではないか。そして、文学テクスト解釈の枠組みそのものの歴史的な歪みやバイアスについてつねに省察する必要があるのではないか。われわれにたいして本書は、そのような問題提起を密かにおこなっているように思われる。
(竹峰義和)