ストローブ゠ユイレ シネマの絶対に向けて
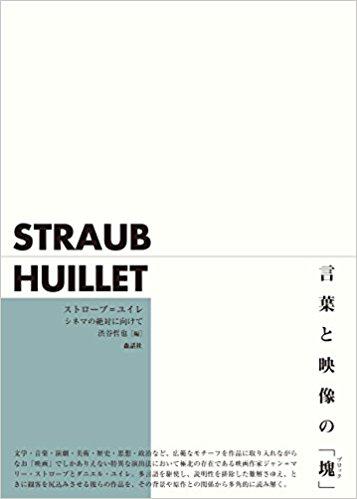
『シネマ』のドゥルーズや最近のゴダールの発言にもみられるように、ストローブ=ユイレの映画はしばしば「石」に喩えられる。「量塊的映画」(小澤京子)としての彼らの映画は堅固な物質性を持ち、それを論じようとする言説を容易に寄せ付けない峻厳さによって際立っている。実際、ストローブ=ユイレを論じようとする試みの多くは、彼らが取り上げる偉大なテクスト(バッハ、シェーンベルク、ヘルダーリン、パヴェーゼ……)の解説に陥ったり、映画製作をめぐる彼ら自身の発言に救いを求めたり、彼らの映画を映画史的な系譜(ブレッソン、グレミヨン……)のうちに溶解させたりして、作品それ自体との遭遇をなんとか回避しようとしていると言っても過言ではない。
日本語で書かれた初めてのまとまったストローブ=ユイレ論集である本書の読みどころは、まずもって、14人の執筆者がどのような戦略でストローブ=ユイレの作品に立ち向かおうとしているのか、という点にある。ストローブ=ユイレの映画作りの特質を目配りよく真っ向から剔出しようとする論考(サリー・シャフトウ、小澤京子、千葉文夫)から、「脚色」の具体的な方法論に繊細な目を向ける論考(渋谷哲也、中島裕昭)、「民族誌映画」や「共産主義のユートピア」といった彼らの映画のキーワードのひとつに着目して、一点突破を試みる論考(金子遊、持田睦)、特定の映画の精読によって作品の肌理に迫ろうとする論考(中尾拓哉、筒井武文)、ストローブその人を訪問したり(伊藤はに子)、ストローブ=ユイレの眷属とも言うべき同時代の現代映画の作り手たちを展望することで(赤坂太輔)、彼らの映画の脱神話化を図ろうとする文章、あえて客観的な解説に徹することで当の文章自体に「石」のごとき堅固さを持たせようとする試み(細川晋)、そしてアドルノやバザンを持ち出してストローブ=ユイレの総体を概念的に捉えようとする試み(竹峰義和、堀潤之)に至るまで、執筆者たちが選択した戦略の多様性は、そのまま、ストローブ=ユイレの映画のもつ豊穣さの反映でもあるだろう。
こうした試みのそれぞれは、確かにストローブ=ユイレの世界の一画をより深く理解するためにはきわめて有益だろう。しかし、本書を通読しても、まだ彼らの映画が論じ尽くされたという感じは受けないし、自戒を込めて言えば、本論集の言葉がはたして彼らの映画に拮
(堀潤之)