ドーピングの哲学 タブー視からの脱却
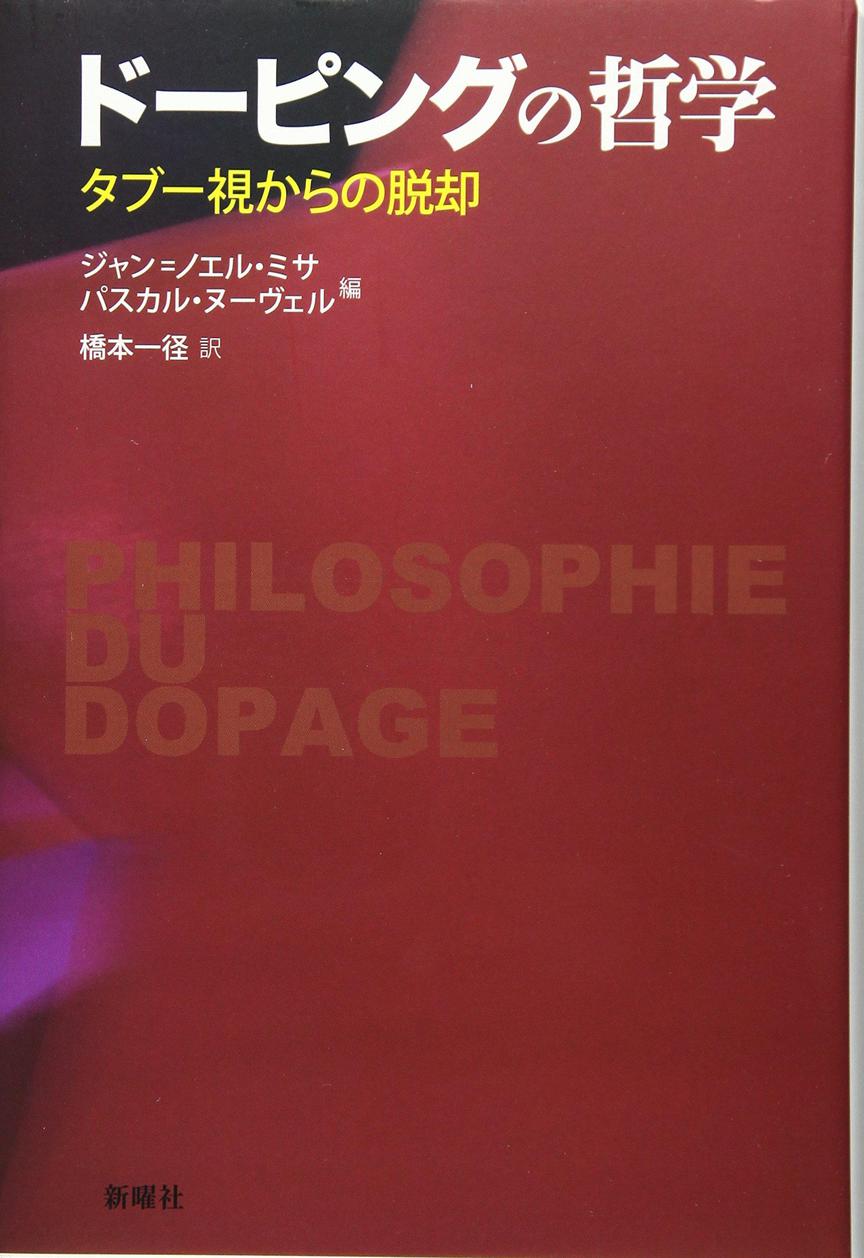
1960年代にオリンピックその他の大会で数々の栄誉に輝いたフィンランドの距離スキー選手エーロ・マンティランタは、生まれつき赤血球の量が一般の人よりも多いという遺伝的な特質を備えていた。今日では合成エリスロポエチンを服用することにより、マンティランタと同じ身体能力を人工的に獲得することが可能である。同じ体質でも、生まれつきならば英雄になれるが、人工的であるとドーピング違反を問われる。この区別を正当化する根拠とは、いったい何なのか。
スポーツが理不尽なほど不平等な世界であることは、誰もが実感していることだろう。同じ練習をしているのに、ぐんぐん記録を伸ばす人と、いっこうに進歩のない私とは、明らかに「モノ」が違う。それでもこれまでは、どちらも「生まれつき」の身体であると言い聞かせて、その歴然たる違いに目をつぶってきた。しかし遺伝子レベルでの解析が進むにつれて、もはやその差異は隠しきれなくなっている。ドーピングの禁止は、そのような差異を「無知のヴェール」で頑なに覆い隠そうする、反動的なそぶりでしかない。
このような思考停止に陥ることなく、ドーピングから、現代社会を考えるための糸口を得ようとするのが、本書『ドーピングの哲学』である。実際、いわゆる「エンハンスメント」医療から、ビタミン剤や栄養ドリンクの日常的な服用に至るまで、私たちの社会は「ドーピング的振る舞い」に満ちあふれている。スポーツのドーピングは、このような現代社会を考えるための格好の材料である。
医師や科学史家、哲学者や社会学者らの11の論考を集めた本書には、西暦2144年のオリンピックで、身体をF1のマシーンのようにチューンナップした選手が、100メートルを7秒84で駆け抜けるという近未来を描いた、SF風の考察も含まれている。学術書の定形をはみ出すこのような型破りな点も、本書の魅力である。
(橋本一径)