映画とキリスト
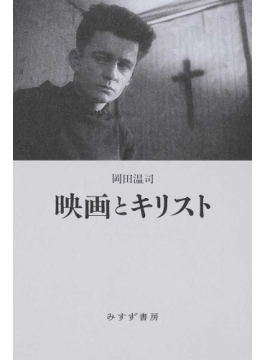
映画と宗教はきわめて近しい関係にあるにもかかわらず、このテーマは「『無宗教』を自認する人の多いわが国」(5頁)で久しく等閑に付されてきた。西洋美術史や思想史のみならず、キリスト教文化や映画にも精通する著者は果敢にもこのテーマに挑む。じっさいに本書をお読みいただければ分かるが、その博覧強記ぶりには改めて瞠目させられる。膨大な数の映画が取り上げられるなかで、それぞれの映画内容に対応する聖書やその外典の記述が掌をさすように参照されるばかりか、文学や絵画、音楽、演劇(オペラ)の諸作品が自由自在に引かれ、映画の「読み方」が次々に更新されていくのである。わけても、古今の有名絵画を縦横無尽に参照して繰り出される緻密な分析はまさに圧巻というほかなく、『映画は絵画のように――静止・運動・時間』(岩波書店、2015年)を上梓した著者の面目躍如たるものがある。
「信者でもない一東洋人に過ぎない」(283頁)と述べ、キリスト教に対してしかるべき距離を置きながら議論を進めようとする著者は、カトリックであるとかプロテスタントであるとかいうことを超えて、より普遍的な「キリスト」を志向しているように思われる。そのことは、自らが浸かっているイデオロギーの正当性を疑わず、ややもすれば教条主義的で一面的なメッセージを発しがちなハリウッド製の諸作品よりも、相対的に意図や結末が曖昧なヨーロッパ映画の肩を持っている点にもあらわれている。したがって、本書では全体を通して「両義性」や「脱構築」、「開かれ」といった概念が重視されることにもなる。
以下、本書の内容を各章ごとに見ていこう。
著者によれば、映画と宗教は「優れて内在的で本質的な関係にある」(32頁)という。そのことを説くのが第Ⅰ章「映画と宗教、あるいは映画という宗教」である。たとえば、若い映画スターの呼称としてしばしば用いられる「アイドル」、マリリン・モンローや原節子のような国民的女優を指す「イコン」、カルト映画という場合の「カルト」など、すべて宗教的な用語が世俗化したものである。くわえて、映画の聖地たるハリウッドのあるロサンゼルスが「天使たち」を意味するとあれば、映画と宗教のつながりの深さはもはやほとんど直観的に了解されるだろう。さらに著者は、映画を「気晴らし(レクリエーション)」のためのものであると同時に、そこに別の世界を立ち上げる「再-創造(レ-クリエーション)」の装置でもあることを看破する。ここでは触れられていないが、著者の記述に刺激されて私が連想した作品として、冒頭のショットで少女による「世界制作」を暗示している『つぐない』(ジョー・ライト監督、2007年)を挙げておきたい。直接的にキリストを描いた映画ではないものの、原題は“Atonement”(贖罪)というきわめて宗教色の濃いものとなっている(原作はイアン・マキューアンによる同名の小説)。「サバト(安息日)」について「本来、サバトは週日(仕事)にためにあるのではなくて、サバトのために週日がある。このことは、シネフィルにとって週末の映画のために週日の映画があるのと似ている」という指摘などは、著者一流のユーモアが発揮されていて楽しい箇所である。もちろん、この章ではアンドレ・バザンの名高い聖骸布の議論にも言が及んでいる。
第Ⅱ章「サイレントのイエス」では、タイトルにある通り、イエスのビオピックを描いたサイレント映画が論じられる。イエスの生涯は「サイレント時代の映画がもっとも好んで取り上げたテーマ」であり、その背景には欧米の観客が「イエスの生涯にまつわる主要なエピソードに大なり小なり通じていた」(34頁)ことがあるという(日本人がやたらと『忠臣蔵』を映像化してきたことと似ているかもしれない)。著者の議論は、リュミエール兄弟の作品を出発点として、アリス・ギィ=ブランシェの『イエスの生涯』(1906年)、シドニー・オルコットの『秣桶から十字架まで』(1912年)、ジュリオ・アンタモーロの『クリストゥス』(1916年)を経由したのち、セシル・B・デミルの『キング・オブ・キングス』(1927年)、ジュリアン・デュヴィヴィエの『ゴルゴタの丘』(1935年)へと至る。
第Ⅲ章「イメージの力、言葉の力、音楽の力」で中心的に扱われるのはピエル・パオロ・パゾリーニの傑作『奇跡の丘』(1964年)である。著者は、本作を「映像と言葉と音楽とが相乗効果となって見事な合体を見せている」(70頁)と高く評価している。これらの要素が具体的にどのように機能しているかについては、ぜひとも本章の美しい議論に直接当たっていただきたい。後半部分では、パゾリーニのルポルタージュ的な手法の特徴を際立たせるために、ロベルト・ロッセリーニの『メシア』(1975年)が比較対象として取り上げられ、検討が加えられている。
第Ⅳ章「変容するイエス像」では主として1970年代以降の映画を取り上げ、イエスのイメージがどのように変わっていったかを追っている。というのも、1970年代にはポストモダンやポストコロニアル、フェミニズムや脱構築といった思想が隆盛し、そうした同時代の潮流が映画で描かれるイエス像にも影響を及ぼしたと考えられるからである。本章で論じられるのは『ゴッドスペル』(デイヴィッド・グリーン監督、1973年)における「カウンターカルチャーのイエス」、『最後の誘惑』(マーティン・スコセッシ監督、1988年)の「神経症のイエス」、『処女のベッド』(フィリップ・ガレル監督、1969年)の「マザコンのイエス」、『ザ・ガーデン』(デレク・ジャーマン監督、1990年)の「クィアなイエス」、『エデンの園々』(アレッサンドロ・ダラートリ監督、1997年)と『少年の名はイエス』(フランコ・ロッシ監督、1987年)の「外典から蘇るイエス」、『サン・オブ・マン』(マーク・ドーンフォード=メイ監督、2006年)の「黒人のイエス」などである。
第Ⅴ章「その子はいかにして生まれたのか」では、マリアの処女懐胎という「不条理」が問題となる。すなわち、映画においてマリアの妊娠と出産がどのように表象されてきたかが論じられる。著者は、1977年公開の『ナザレのイエス』(フランコ・ゼフィレッリ監督)で、陣痛に苦しむマリアの姿がおそらく映画史上はじめて描かれる意義を強調する。1990年代に入ると堰を切ったようにマリアの妊娠・出産を描く映画があらわれはじめる。ここでは『ナザレのマリア』(ジャン・ドラノワ監督、1995年)、『息子の娘マリア』(ファブリツィオ・コスタ監督、1999年)、『マリア』(キャサリン・ハードウィック監督、2006年)の妊娠・出産にまつわるシーンが分析の俎上に載せられ、女性の社会進出やフェミニズム思想の影響が指摘される。本章ではこのほかに『ゴダールのマリア』(ジャン=リュック・ゴダール監督、1984年)、『イオ・ソーノ・コン・テ』(グイド・キエーザ監督、2010年)、『ヴェラの祈り』(アンドレイ・ズビャギンツェフ監督、2007年)が取り上げられる。
第Ⅵ章「脇役たちの活躍」で主役を張るのは、一般にキリストの物語で脇役とされてきたイスカリオテのユダとマグダラのマリアである。まず、『サタンの書の数ページ』(カール・ドライヤー監督、1920年)、『ジーザス・クライスト・スーパースター』(ノーマン・ジェイソン監督、1973年)、『キング・オブ・キングス』(ニコラス・レイ監督、1961年)、『偉大な生涯の物語』(ジョージ・スティーヴンス監督、1965年)、『ナザレのイエス』(フランコ・ゼフィレッリ監督、1977年)に登場するユダたちの多彩な描かれ方に注目し、映画製作当時の時代背景にも眼を配りつつ、それぞれの独自性を明らかにしていく。さらに、ユニークなマグダラのマリア像を提示している作品として『マリー〜もうひとりのマリア〜』(アベル・フェラーラ監督、2005年)や『愛に関する短いフィルム』(クシシュトフ・キェロフスキ監督、1988年)などが論じられる。
第Ⅶ章「キリストに倣って」では、映画に投影された「鏡」としてのキリストのイメージが「受難」「メシア」「復活」「贖い」といったキーワードに基づいて検討される。まずは『田舎司祭の日記』(ロベール・ブレッソン監督、1951年)、『冬の光』(イングマール・ベルイマン監督、1963年)、『ナサリン』(ルイス・ブニュエル監督、1959年)の三本の分析を通して、キリストの「受難」に倣った聖職者たちの三者三様の姿を浮かび上がらせる。つづいて、「メシア」に倣ったアンチヒーローたちの系譜が辿られたあと、『田舎司祭の日記』の「受難」と対をなすように、めでたく「復活」を遂げる現代のキリストを描いた作品としてブレッソンの『抵抗(レジスタンス) 死刑囚の手記より』(1956年)が取り上げられる。そして最後に「贖い」をテーマとする西部劇やフィルム・ノワール、マーティン・スコセッシの諸作品に論及している。
第Ⅷ章「『聖なる愚者』たち」では、「救済」を求めて非合理的な「犠牲」に身を投じる「聖なる愚者」の姿を描いた映画が論じられる。ここで取り上げられるのはアンドレイ・タルコフスキーの『ノスタルジア』(1983年)と『サクリファイス』(1986年)、ロベルト・ロッセリーニの『神の道化師、フランチェスコ』(1950年)、カール・ドライヤーの『奇跡(御言葉)』(1954年)といった名だたる作品たちである。つづいて「神なき時代のメシアが思考され(アガンベン)、弱い神が積極的に評価されるようになる(ヴァッティモ)、ポストモダンと脱構築の時代」(263頁)にふさわしく、言い知れぬ不気味さや人を不安にさせるような性質を持った現代の「聖なる愚者」のイメージを提示した作品として『スリング・ブレイド』(ビリー・ボブ・ソーントン監督、1996年)、『ユマニテ』(ブリュノ・デュモン監督、1999年)、『島』(パーヴェル・ルンギン監督、2006年)を分析している。
キリストを意味するイタリア語の名詞「クリスト」を女性形にした造語をタイトルに冠する第Ⅸ章「『クリスタ』たち」で考察されるのは、文字通り、女性がメシアの機能を担う作品である。まずは、二十世紀後半のフェミニズム思想の動向と軌を一にしてあらわれた1980年代以降の三本の映画『バベットの晩餐会』(ガブリエル・アクセル監督、1987年)、『ショコラ』(ラッセ・ハルストレム監督、2000年)、『バグダッド・カフェ』(パーシー・アドロン監督、1987年)の分析を通して、女メシアたちがちらつかせている魔女のイメージを浮かび上がらせる。つづいて、これらの女性たちとは異なるパターンのクリスタとして、「無償の愛と犠牲」を体現した「聖なる愚者」の系列に位置づけられるような女性が論じられる。そこで取り上げられる映画はラース・フォン・トリアーの『奇跡の海』(1996年)と『ダンサー・イン・ザ・ダーク』(2000年)、フェデリコ・フェリーニの『道』(1954年)と『カビリアの夜』(1957年)などである。
第Ⅹ章「瀆聖」では、教会や信者たちから「瀆神的」だと批判された映画に検討が加えられる。具体的には、『銀河』(ルイス・ブニュエル監督、1969年)、『モントリオールのジーザス』(ドゥニ・アルカン監督、1989年)、『ドグマ』(ケヴィン・スミス監督、1999年)、『ローマ法王の休日』(ナンニ・モレッティ監督、2011年)などである。「瀆聖」とは、「聖なるものの傍らにあって、聖なるものから自由になる」こと、すなわち「既存の規範や制度から解き放たれる」ということを意味する(316頁)。ここで論じられているのは、そうした意味において「自由」な映画たちなのである。
以上、全十章の内容をそれぞれざっと要約してみたが、「新刊紹介」というにはいくぶん長く書きすぎてしまったかもしれない。本書で論じられている映画作品が具体的にわかるように、できるだけタイトルを挙げたつもりだが、これでも論及されている作品のうち、かなりの数を落としている。お馴染みの古典作品から現代の話題作までを幅広く取り上げ、それらの作品が隠し持つ有意義な細部に拡大鏡を当てて次々と新たな読みを提示してみせる著者の鮮やかな手つきは、「映画とキリスト」という本書のテーマに関する理解を深めてくれるのみならず、映画を見る我々の眼そのものを鍛えてくれるだろう。
(伊藤弘了)