表象の京都 日本映画史における観光都市のイメージ
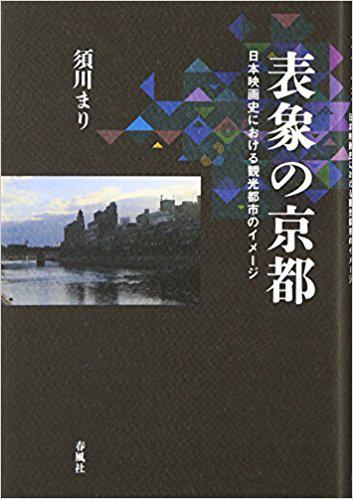
本書は、京都の観光や都市に関する言説を踏まえつつ、戦後から現代にかけて同地でロケーション撮影された、いくつかの現代劇映画に登場する京都の表象を分析した研究である。
本書の構成を概観したい。第一章は、『偽れる盛装』(吉村公三郎監督、1951年)の作品論が展開される。著者は、同作品と『祇園の姉妹』(溝口健二監督、1936年)の共通点として、匿名性と固有性の両面をもつ京町家に着目し、溝口が在住者の視点から「外」の視線を遮断して京町家を描いたのに対し、吉村が戦後の観光者の視線を導入し、京町家の「内」と「外」の往還を表現したことを指摘する。第二章は、まず『カルメン故郷に帰る』(木下恵介監督、1951年)が取り上げられ、戦後の文化概念が揺れ動いていたさまが論じられる。その上で、『晩春』(小津安二郎監督、1949年)や『宗方姉妹』(同、1950年)、TVドラマ『青春放課後』(里見弴・小津共同脚本、1963年)に表出した小津の京都への視線は、「不易なる変容」としての京都の文化を体現していたことが述べられる。第三章は、「観光映画」として『東京物語』(小津監督、1953年)を論じた後、『斑女』(中村登監督、1961年)や『古都』(同、1963年)のエスタブリッシング・ショットの分析から、中村作品に描かれた京都と高度経済成長期の観光との関係が考察される。第四章は、『お引越し』(相米慎二監督、1993年)や『マザーウォーター』(松本佳奈監督、2010年)にみられる鴨川の表象を分析し、それが外部から京都に神秘性を求める視線にもとづいていることが指摘される。第五章は、『カントリーガール』(小林達夫監督、2012年)や『舞妓はレディ』(周防正行監督、2014年)から、現在の京都と観光の関係が概観された後、現代劇映画に描かれる京都の「日本らしさ」は、初期映画のジャポニスムに起源をもつことが明らかにされる。
全体として、撮影所の存在によって時代劇映画に偏重してきた京都映画史を、観光というテーマを手がかりに、現代劇映画にみられる都市表象の分析から再考するという視点は、本書が示すとおり、有効であるといえるだろう。ただし、映画史の観点から些か疑問を生じる箇所もあり、たとえば第三章の「文化映画の定義が不明瞭」(153頁)という記述は、たとえ広義のアクチュアリティ映画およびドキュメンタリー映画を包摂する文化映画の例示を意図していたとしても、少なくとも映画法による文化映画の定義に言及しておくべきだったと思われる。文化映画がKulturfilmの訳語であり、映画法もドイツの文化法制が参考にされたことはいうまでもない。このことは、本書が第二章を通じて理論的に依拠する西川長夫の研究、すなわち文明概念への対抗としてドイツから文化概念が導入されたという議論を裏づけることにもなるからである。
ただし、これらは枝葉末節にかかる一例であり、本書が戦前の溝口健二作品や小唄映画、また現代のアニメーションに言及していることからも、京都の同時代表象と現代劇映画の関係は、より広いパースペクティブから捉えられるべき魅力的なテーマとして、著者の更なる研究の展開が期待されるだろう。最後に、これは著者ではなく編集者の責任であるが、論旨に関わるいくつかの致命的な誤記は、すぐれた論述が妨げられるだけに、残念に思われる。
(上田学)