Media Theory in Japan
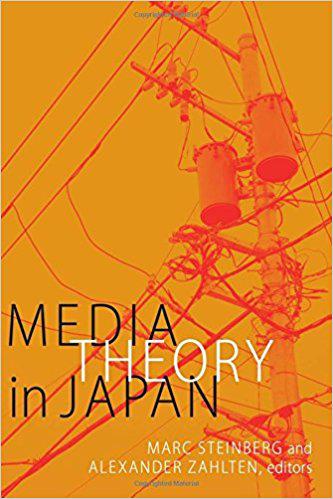
タイトルの通り、日本のメディア理論を扱ったアンソロジーである。しかし、その内容は多岐にわたり、すべての章が明示的にメディア理論について論じているわけではないし、メディア理論というグランド・セオリーの各論として日本という地域を扱うことのみが本書の課題なのでもない。もちろん、日本におけるマクルーハンとエンツェンスベルガーの受容(マーク・スタインバーグ、ミリアム・サス)、日本の初期テレビ理論(アーロン・ジェロ—)、東浩紀のメディア理論(門林岳史、トム・ルーサー)、中井正一のメディア理論(北田暁大)など、直接的にメディアについての理論的言説を扱った章もあるが、他方で京都学派、小林秀雄、ニュー・アカデミズムを扱った章(ファビアン・シェーファー、北野圭介、アレクサンダー・ザルテン)や、建築とサイバネティクス理論を論じた章(古畑百合子)のように、直接メディアについて論じているというよりは、メディアないし媒介性をめぐる概念化が問題になっている章もある。あるいは雑誌『インターコミュニケーション』(マリリン・アイヴィ)、1980年代のマーケティング言説(依田富子)、ナンシー関とろくでなし子のメディア言説/実践(御園生涼子、アン・マクナイト)のように、メディアをめぐる言説空間とそのなかでの実践を対象としている章もある。しかし、本書全体を通じて明らかになるのは、むしろその三者を明確に区別できない、あるいはするべきではない、ということである。編者による序文が明確にしているように、本書がむしろ目論んでいるのは、日本という場所を媒介として、メディア理論そのものを問題化することである。もちろん、「日本」の「メディア」「理論」についての各論的な知識を補うにあたっても有益な研究書であるが、それと同時に、リピット水田堯による序とマーク・B・N・ハンセンによる後記も含め、本書はメディア理論という曖昧な研究領域をより複雑かつ生産的に実践するにあたっての手引きともなるだろう。
(門林岳史)