単著
20世紀ロシア思想史 宗教・革命・言語
岩波書店
2017年2月
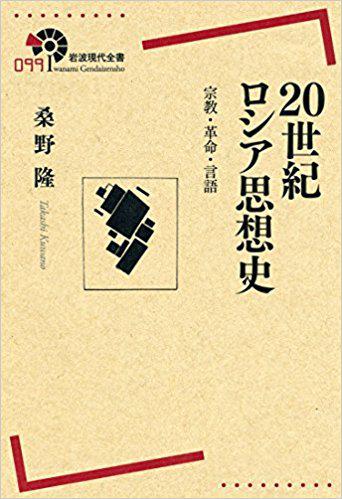
19世紀末から21世紀初頭まで、ソ連という途方もない実験を試み閉ざした100年あまりの思想史を、250頁のうちに一望できる著者はほかにいない。描き出された広大な地図は、初めてこの土地に足を踏み入れる者だけでなく、この土地をよく知ったつもりの者にとっても発見に満ちている。地図になってこそ見える地形があるのだ。たとえば「一」と「多」を両立させようとする思想の痕跡が、19世紀末の宗教哲学者ソロヴィヨフの「全一性」概念から、戦間期の亡命知識人による「ユーラシア主義」、戦後の記号論の泰斗イヴァノフまで、綿々と浮かびあがる。あるいはイタリアとロシアの未来派を比較して、前者の機械礼讃に対し、後者は有機的生を貴んだという指摘から、バフチンへ、あるいはスターリン期ソ連の社会主義リアリズムへとつながる線がまた浮かぶ。自分の庭を囲って愛でているばかりの者には、このような視野を与える仕事は決してできない。個人的に思い出すのは、かつて学部生のころ、著者と貝澤哉の対談「ロシア・イデオロギー」(『現代思想』1997年4月号)によって、ロシア現代思想という地図を初めて与えられ、そこで言及された本を留学先で探し集めまわったことだ。本書はそれ以上の地図として、数多くの読者を導いてゆくにちがいない。
(乗松亨平)