アメリカン・アヴァンガルド・ムーヴィ
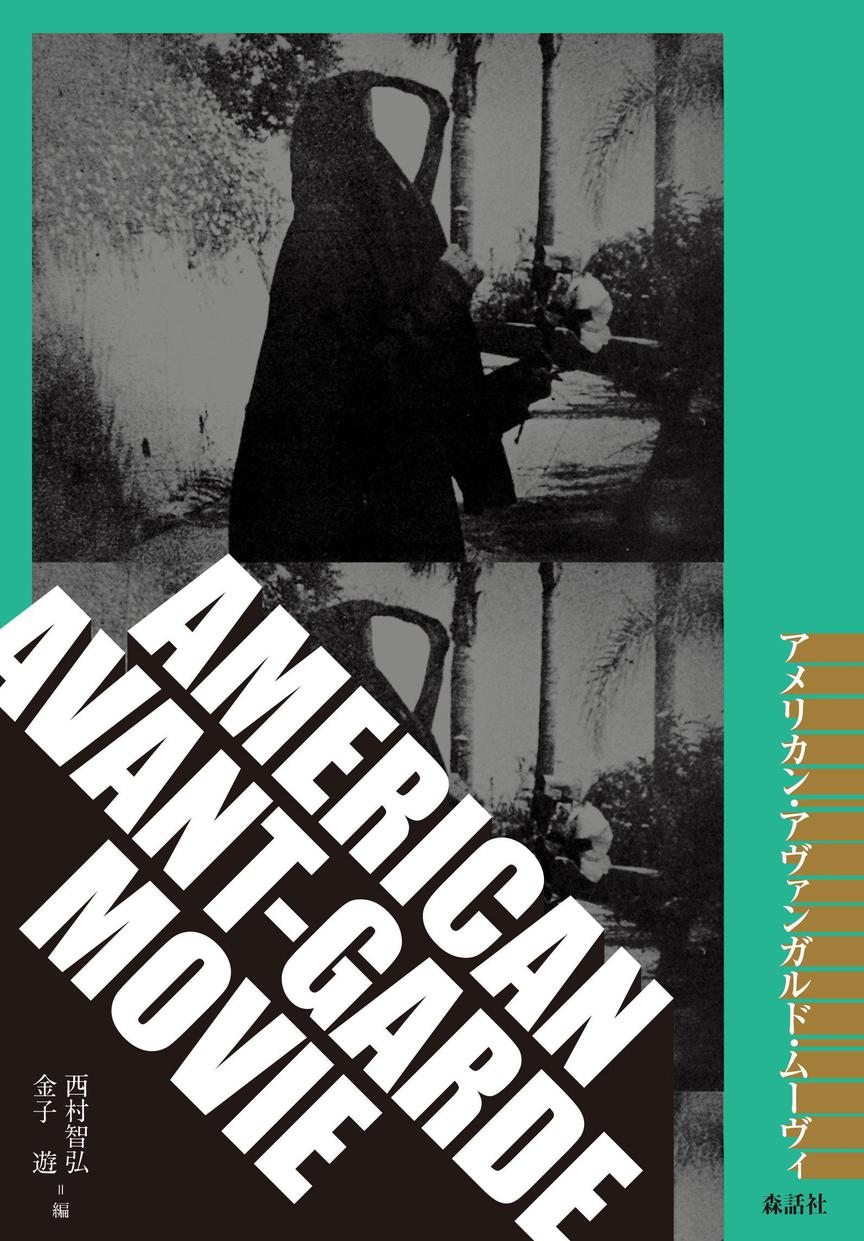
1950年代から現代に至る、アメリカ前衛映画・実験映画の系譜を多角的に照らす論集。前衛映画・実験映画を、多様で異種混淆的なコンテクストに開こうとしているところが、本書を現代的にしている。以下、各論の簡単な紹介を。
越後谷卓司は、1950‐60年代に隆盛したアメリカ実験映画を、戦前ヨーロッパのアヴァンギャルド映画と、ヴィオラやゴダールら20世紀末の映像表現の文脈に結びつける。
金子遊は、ハイチにおけるマヤ・デレンの一種の「映像人類学者」としての活動から現れるダンスするカメラの姿を、著者自身の生と共鳴させながら浮かび上がらせる。
太田曜は、フリッカー映画の元祖としても知られるペーター・クーベルカの作品と理論を、著者が受けたクーベルカの授業内容も含めて紹介。「料理」の授業がおもしろい。
西村智弘は、アンディ・ウォーホルのファクトリーにおける多様な活動の交錯点としての映画を描く。「がらくた」に惹かれるウォーホルとその映画の初々しさが本当に魅力的だ。
ジュリアン・ロスは、拡張映画を「パフォーマンスとの融合」という新たな観点から分析。キャロリー・シュネーマンやトリシャ・ブラウンのハプニング/ダンス/映画に光を当てる。
阪本裕文は、構造映画の代表マイケル・スノウの諸作品を、ロザリンド・クラウスの「技術的な支持体」という概念を通して、メディウムの物質性を超える探求として再考する。
平倉圭は、ロバート・スミッソンによる異種混淆的な映画/テクスト/アース・ワーク「スパイラル・ジェッティ」を詳細に分析し、心‐物複合的な「思考」をそこに見出す。
吉田孝行は、セオドア・カジンスキー(「ユナボマー」)が潜伏した山奥の小屋を再現して映画に撮るジェームス・ベニングの試みから、「建築映画」の現在的可能性を論じる。
自身もニューヨーク州立大学ビンガムトン校で実験映画の制作を教える西川智也は、現在のアメリカ実験映画をとりまく上映・制作・教育環境の新たな活況を伝えてくれる。
岡田秀則は、映画をつくることと同じ程に、映画を保存し「分かち合う」ことに情熱を注ぐ、ジョナス・メカスとアンソロジー・フィルム・アーカイヴスの活動を紹介する。
アメリカ前衛映画・実験映画の多様性は、映画史・美術史・演劇/ダンス史を横断的に見ようとするとき重要な視座を与えるだろう。本書もまた、新たな読者=観客との「分かち合い」へと開かれた本だ。目次・著者紹介はこちら。
(平倉圭)