「J演劇」の場所 トランスナショナルな移動性へ
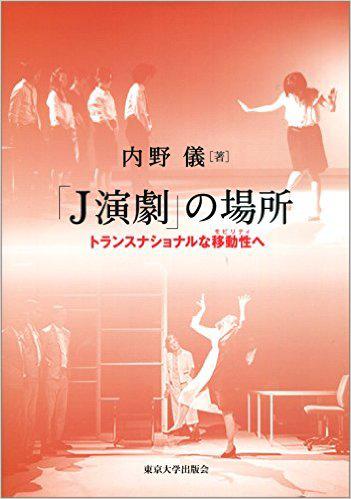
アメリカ演劇研究の牽引者であると同時に、日本の同時代演劇の状況に批評的に併走しつづけてもいる著者が、2001年頃から現在にかけて様々な媒体に発表してきた論考を、いくつかの書き下ろし原稿を加えつつ集成した著作である。本論は三部に分かれており、まず第Ⅰ部「現代アメリカ演劇研究の地平」では、モダン・ドラマからパフォーマンス・アート、マルチメディア演劇へと到る20世紀アメリカ演劇の流れが、その研究史も含めて通覧され、第Ⅱ部「J演劇を理論化する」ではここ十五年間ほどの日本の同時代演劇の展開が、とりわけ岡田利規、清水信臣、宮沢章夫の三名を重要な参照項としつつ、現象的な記述に留まることなく考察される。そして第Ⅲ部では、アメリカや日本といった国民国家的枠組では把捉しきれない「グローバル化した世界」──それは「場所」というよりも「トロープ」であると著者はいう──におけるパフォーマンスの実践や理論的な諸問題が扱われる。演劇に対する学術的な関心から本書を手にする者にとっては、とりわけ第Ⅰ部におけるモダン・ドラマの読み直しや、ドラマと上演の関係の再概念化に関わる理論的な作業から裨益するところが大きい(舞台芸術関係の文献がほとんど翻訳されない日本の状況を鑑みるに、マーティン・プッチナーやシャノン・ジャクソン、W・B・ウォーゼンといった人々の議論が導入されたことの意義は特筆に価するものだ)だろうし、第Ⅲ部の議論はパフォーマンス研究の問題設定の広がりの一端を提示するものとして、他領域の研究者たちにも興味深く読めるものだろう。第Ⅱ部の議論は研究者や人文書読者の範囲を超えて、同時代の演劇実践に関心を持ったり、携わったりしているあらゆる人々に刺激を与えるはずだ。
アメリカ、日本、グローバル化した世界という複数のフィールドを行き来する本書であるが、「J演劇」という言葉がタイトルに冠せられていることから推察されるように、著者の関心の中心は日本の同時代演劇状況にあるとひとまずいえる。しかし、それは「日本の演劇」というものを実体的に措定するためではない。「日本を根拠や定点や規範とすることなく単なる〈媒介〉とする、西洋とアジアの両方向に開かれた芸術実践」(ⅴ頁)を構想可能にすることこそが、著者の意図するところである。
しかし、著者自身が述べていることだが、本書に収められた、執筆の時期も媒体も異なる論考間に「主題的一貫性」というものはあまり感じられないかもしれない。だが、それは本書の瑕疵を単純に意味するのではない。本書のキー・コンセプトのひとつが、上述したような「根拠や定点や規範」の設定に抗う〈移動性〉であることも、そうした非一貫性をある程度正当化する──「落ち着きのない動きっぱなしの〈受動性〉(=動いてしまっている)のうちに、これらは書かれたものだ」とも著者は述べている(ⅵ頁)──ものであるだろうが、それ以上に、論じるべき対象への体を張った接近が、安定的なパースペクティヴの獲得よりも優先されていることが重要だ。著者がしばしば用いる言葉を借りるならば、これは「現場的」に書かれた書物なのである。しかし、現場に飛び込む著者の真摯さと果敢さを、例外的なものとしてここで称えたいのではない。パフォーマンスという対象のエフェメラルな性質が、そのような現場的なスタンスを必然的に要請するということが問題なのだ。だから、本書の非一貫的=現場的なありようは、パフォーマンスを研究する者たちそれぞれに、自らの位置性を再考させる契機となる。
もちろん、現場的であることは近視眼的プラグマティズムを思弁に優越させることを意味しはしない(本書の中では「業界的」という言葉が否定的に用いられる)。著者の考察には、常に「理論化」への意志がある。その成果でもあるわけだが、収められた論考の多くを初出時に読んでいた一人としていうならば、書物というかたちに組み立てられ、新たに配列されなおしたそれらは「まとまり」を獲得しすぎてしまっているようにも思える。だが、私たちはそれを再びバラして読むこともできる。しかも、それは随意に読むというよりもむしろ、執筆の順序、発表の順序、論理の順序、対象(出来事)の順序といった複数の時間性の交錯と断絶を精緻に探索することであるだろう。書物の(表向きには)静的な秩序に抗して、そこに込められた非同期的な複数の時間を再活性化する。そうすることによって、著者の思考した現場を共有し、それと新たな別の交渉可能性を開けるのではないだろうか。
(江口正登)