単著
夜の哲学 バタイユから生の深淵へ
青土社
2016年9月
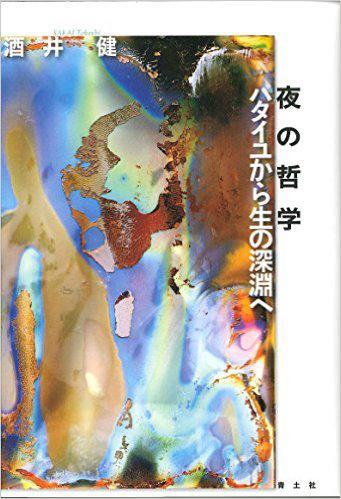
本書はフランスの作家・思想家であるジョルジュ・バタイユの思想を導きの糸としながら、バタイユ研究者である筆者が広義の哲学の源泉へと遡る「夜」の思考を展開した書物である。
ここでいう「夜」の思考とは、筆者によれば不合理で確固たる基盤をもたない思考であり、理性的かつ科学的な知にかかわる「昼」の思考とは一線を画すものである。そのような「夜」は、「昼」の光の眩しさに掻き消され、そこに同化吸収されうる弱さをもちながらも、生の豊かさを内に秘め、時にはこれを自由に発露させるものでもある。筆者はこうした「昼」と「夜」の思考がせめぎあう境界線上に身を置きながら、両者の葛藤を、そして「夜」の不合理さが孕む「夜」それ自身の内部の葛藤を生き抜き、体験しているといえるだろう。
そのため、筆者のまなざしはバタイユ思想解釈にのみ向けられているのではない。鎌倉時代末期に編まれた『一言芳談』からはじまり、未曽有の被害をもたらした東日本大震災や原子爆弾を投下されたヒロシマ、さらには岡本太郎や三島由紀夫へと「夜」の思考は移りゆく。ニーチェやブランショ、ラカンやサドについても触れながら、「夜」に隠された生の根源を見出そうとするバタイユと筆者の姿が重なる本書は、たんなる西洋哲学史や構築された既存の哲学体系とは異なる自由な思考としての哲学の在り方を明示しているのである。
(横田祐美子)