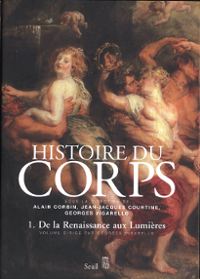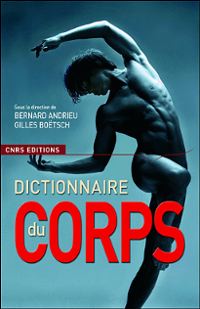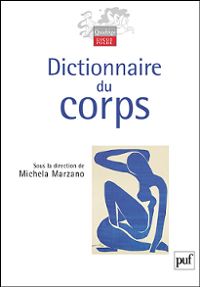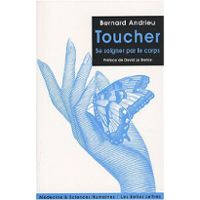| 海外の研究動向 |
|---|
フランス身体論の現在——解体から再構築へ
橋本一径
フランスでは「身体」をテーマとする書物の刊行ラッシュが続いている。アラン・コルバン、ジョルジュ・ヴィガレロらを編者とする『身体の歴史Histoire du corps』(Seuil)全3巻のシリーズが完結したのが、2006年。同年にはベルナール・アンドリューらの編による『人文・社会科学における身体辞典Le dictionnaire du corps en sciences humaines et sociales』(CNRS Edition)が刊行され、これを追うようにして翌年にはPUFからも『身体辞典Dictionnaire du corps』(ミケラ・マルザノ編)が上梓された。人文・社会科学系の「身体辞典」が、しかも2冊も刊行されている国というのも、おそらく珍しいのではないか。B・アンドリュー編による前者は2008年になって、より廉価な新版も刊行されている。やはりアンドリューが編集委員に名を連ねる学術誌『身体Corps』(http://www.cairn.info/revue-corps.htm)も、2006年から刊行が開始され、「スポーツの身体」「身体と色」「食べる身体」などのテーマを毎回掲げながら、現在までに6冊を世に問うている。この雑誌の編纂に携わる面々による論集の刊行も相次いでおり、ニベア研究所の協力による『皮膚La peau』(CNRS Edition, 2008)、身体と色をめぐってのアンソロジー『Coloris Corpus』(CNRS Edition, 2008)、やはり同じテーマの図録集『身体と色Corps & Couleurs』(CNRS Edition, 2008)が、矢継ぎ早に出版された。日焼けの歴史、脱毛の歴史、人体実験の歴史、等々、身体にまつわる様々な習慣などを扱った最近の刊行物も付け加えれば、リストは一段と膨れ上がるだろう。
「身体の世紀」。『身体の歴史』シリーズ完結に際して『ルモンド』紙(2006年2月3日)に掲載された書評のなかで、記者のフィリップ=ジャン・カタンシは、20世紀という時代が、「精神」の優位の名のもとに長らく拒絶されてきた「身体」を、文字どおり発明したのだと語る――その「発明品」にはもちろん、ボディー・ビルダーの身体や「エステ」の身体などと合わせて、強制収容所において拷問を受ける身体という、不吉な形象も含まれている。編者のひとりのヴィガレロも、同じく『ルモンド』紙に掲載されたインタヴューにおいて、シリーズの出発点にあったのが、今日の社会において身体が「ほとんどカルト的な」崇拝の対象になっていることへの驚きであったことを認めている。その上でこの『身体の歴史』のシリーズは、現代における「身体」への強い関心が、過去における「身体」を過度に抑圧されたものとして描いてしまいがちだとの反省から、ルネサンス以来の言説が「身体」をどのように表象してきたのかを、テクストやイメージなどの多彩なコーパスを駆使しつつ、総合的に提示することを目指したものである。(なおこの『身体の歴史』全3巻の日本語版は、藤原書店より近日刊行が開始される予定であることも付け加えておきたい。)
言うまでもなく、これらの書物は、「身体とは何か」という問いに対して、直接的な答えを出そうとするものではない。そこに描き出されているのは、礼儀作法やスポーツなどの様々な身体の所作であったり、体液や血液、さらにはDNAであったり、労働者や兵士の身体に加えられる暴力であったりするかもしれないが、「身体」そのものは不在であるとさえ言えるのだ。マルザノ編の『身体辞典』には、「キリストの身体」「器官なき身体」などの項目はあっても、「身体」という項目自体が不在なのは示唆的である。もちろんこのことは編著者たちも十分に意識的な点であるに違いない。彼らが俎上に載せているのは、「身体」自体ではなく、「身体」をめぐって紡ぎだされてきた、レトリックであり、表象であり、様々な所作である。そして「身体」は、そうした言説から常にこぼれおちるところにある。「身体という他者によって語らされているのであって、その他者に語らせているのではない」。身体と歴史記述にかんして、ミシェル・ド・セルトーはかつてこのように述べていた(L’absent de l’histoire, 1973, p. 179)。そのような社会的な言説の生産活動の総体こそが、あえて言えば「身体」だということになるのかもしれない。
「身体」の不在の確認に行き着くような、構造主義の流れを汲むこれらの著作群のなかにあって、ベルナール・アンドリューの一連の仕事は、異彩を放つものであるように見受けられる。身体障害者に対する不妊手術という優生学的な問題や、エイズ患者の置かれた境遇など、医学がもたらす社会的な影響をこれまでの考察の一部としてきた哲学者のアンドリューにとって、「身体」とは、不在であると結論づけるだけでは、おそらく不十分である。というのも「身体」は、たとえば臓器移植の現場においては、その法的なステータスが不在だからこそ、様々な問題を引き起こしているからである。最近の著作のひとつである『触覚Toucher』(Les Belles Lettres, 2008)において、彼がマッサージやタラソテラピーなどに着目するのも、専門に分化した西洋医学が、身体のまとまった像を結ぶことができなくなったことへの反省に基づくものだろう。「身体」が社会的な構築物であるとすれば、それを確認して事足れりとするのではなく、新たに構築しなおす方途を探るべきである。そのような問題意識に貫かれたアンドリューの仕事が、近年では「皮膚」「触覚」「日焼け」など、身体の境界面をめぐって繰り広げられているのは、当然の帰結であると言えよう。身体の輪郭線を新たに確定しなおそうとする彼の試みは、かつてディディエ・アンジューが精神分析学的な観点から「皮膚=自我」として練り上げたのとはまた別の、「表面」をめぐる思考として、結実しつつあるようである。
橋本一径(武蔵大学)