ハイデガーと生き物の問題
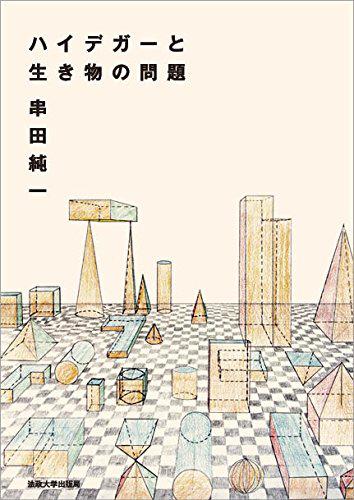
ハイデガーの動物論が、デリダ、ドゥルーズ、アガンベン、他に誰を取り上げるのであれ、現代思想の一大テーマとなってきたことは、多少の事情通であれば、すでに承知のことだろう。ハイデガーの哲学は日本語圏ではもっぱら『存在と時間』(既訳が七種類もある!)を中心に受容されてきた観があり、ハイデガーの動物論──本書の言葉に従えば「生き物」論──に正面から取り組んだまとまった研究は、これまで存在しなかった。本書は、そうした状況を打開する最初の貴重かつ重要な一歩を踏み出した力作である。
ハイデガーの動物論の主要部は、全集第29/30巻『形而上学の根本諸概念──世界 - 有限性 - 孤独』に収められている。1929~30年に行われた講義録として1983年に出版されたこの巻は、フッサールの高弟のオイゲン・フィンクなど一部では「隠れた主著」と呼ばれるほどに高い評価を得ていた。しかし刊行されたのは、ハイデガーの死後七年後の1983年(日本語訳は1998年)であり、動物論や退屈論を主題にしているこの講義は『存在と時間』の基礎存在論の企図からすれば逸脱のようにみえ、その重要性が必ずしも十分に理解されてきたわけではなかった。
そのような状況のなか、この講義に真正面から取り組むことにより、掛け値なしにその意義を示したことが本書の功績である。それは本書が、現代思想のみならず近現代の生物学の拡がりを視野に収めた、バランスよく目配りの効いた視座からこの動物論を説明しているからというだけではない。本書が、端的にハイデガー研究としても、『存在と時間』との関連はもとより、その企てが背景とする哲学的ないし哲学史的な文脈(とくにアリストテレス、ライプニッツ、シェーラー)をも押さえつつ、この動物論をハイデガー哲学の変遷のなかで的確に位置づけているからである。
したがって本書は、ハイデガーをきっかけにして哲学的動物論というひとつの目新しいトピックを器用に取り出して論じてみせたという類いのものではなく、まさにハイデガー思想の核心に迫る研究である。かといって、従来のハイデガー研究にありがちな、編年史的な整理に基づく文献学的記述に終始しているわけでもない。これは、ハイデガーの思想に即しながら、当の主題内容に応じて一定の体系的な構成を備えた「生き物の哲学」研究でもある。以下、そうした利点に留意しつつ、そのあらましを追ってみよう。
序論ではまず、デリダのハイデガー論を手がかりに、デリダの立論をも明確にするような仕方でハイデガーの動物論のかかえる人間中心主義の問題が提示されたうえで、その「生き物の哲学」を問うための意義が説明されている。続けて第一章では、ハイデガーのアリストテレス『形而上学』講義にまでさかのぼって能力一般の超越論的条件を究明する仕方で『形而上学の根本諸概念』の諸前提が確認される。さらに第二章では、ハイデガーの形而上学的探究が、基礎存在論とメタ存在論の二重性を孕んだ困難な企てとして示されたのちに、『形而上学の根本諸概念』のひとつの主軸である退屈論へと接続される。しかしこの理路はある袋小路に行き着かざるをえない。いわばそこからの脱出口として、探究のもうひとつの主軸にハイデガーが設定したのが、まさしく動物論にほかならない。
第三章と第四章は本書の中核をなす。ここでは、基礎存在論とメタ存在論の二重性が、現存在にとっての生き物一般をめぐる存在了解(第三章)と、それに関する現存在(人間)自身の存在解釈(第四章)の二重性へと変奏され、論じ直されることになるだろう。とりわけ第三章は、本書の主題からしてもっとも重要な部分であり、ハイデガーの立論を、ユクスキュルやダーウィン主義のみならず近現代の生物学の知見から位置づけ直し、「超越論的な生き物の哲学」として再構成してゆく手際は、本書の面目躍如たる部分である。
第四章は、第三章と対をなすかたちで佳境に入ってゆく。この章は、人間という現存在の能力ないし潜勢力そのものについて取り上げ、ライプニッツのモナド、シェーラーの(衝動インパルスの)抑止ないし脱抑止といった主題との関連で、ハイデガーの「超越する生き物の哲学」を探究している。そこから明らかにされるのは、現存在に固有の世界形成能力が「為さない必要も為す必要もない」に耐えられない窮迫した情動、すなわち「退屈」と表裏一体になっているということにほかならない。根本的なのは、現存在の企投的な構造にあっては、ただ何もしないでいることすら、そのような情動に根底ではあらかじめとらわれざるをえないということなのである。
ここにあって形而上学の深淵を見出したハイデガーは、ある意味で言葉を失い、それ以後いっそう散文的ないし断片的な思索へと彷徨い出していったかのようにみえる。本書が興味深いのは、そこからハイデガーから少しずつ距離とってゆく仕方で、言葉を失うことそのものを経由して言葉固有のあり方が現存在に引き起こす諸契機の考察へと向かっている点にほかならない。具体的には、ヘルダーリンと対照的なかたちでリルケの即興詩を取り上げ、詩の言葉を紡ぎだす詩人の形象のうちに、人間以後の「脱抑止する動物」とも言うべき、現存在のいまだ不分明な運命を見定めようとするのである。
付言すれば、著者が手塚富雄とハイデガーとの対話を最後に引き、また「結びに代えて」では、紀貫之の言葉のうちに大和言葉に潜む存在論的な構えを示唆しているように、本書は、西洋的ロゴスの伝統をめぐって日本語で哲学することの意味に対しても無関心ではない。おそらく読者はそうした段階を経て最後に、ハイデガーのなかからハイデガーを突き抜けて著者本人の思考が立ち上がろうとしている地点を目撃するのである。
それは、いまだ控え目な仕方ではある。しかしながら「生き物の哲学」探究としてはいささか意外とも思われるかもしれない本書の帰趨は、そこへといたる動物論の諸問題を通じて『存在と時間』以後のハイデガー哲学の全容が浮かび上がってくる射程を明確に示しているのであり、そしてなによりも、そこからまた、ハイデガー自身を超えて動物論そのものの新たな可能性を考えるよう、読者を促しているのである。
(宮﨑裕助)