市民参加型調査が文化を変える 野尻湖発掘の文化資源学的考察
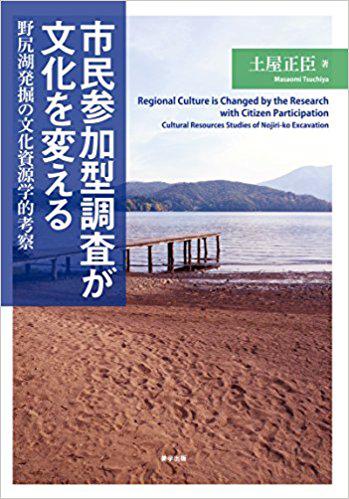
アカデミックな知を相対化する──読み終えた後にこの言葉が頭に浮かんだ。
野尻湖をフィールドに半世紀に渡り現在も続く、市民の参加に開かれた埋蔵考古資料発掘調査。現在まで21回にも及ぶ発掘プロジェクトの進行を活写することで、時代の変化にともなうダイナミズムが浮き彫りになる。学術、行政、社会の交流を教育プロセスとして枠づけることで、文化財保護行政を社会教育の現場としてとらえ直す試みである。著者の土屋氏は、國學院大学で考古学を修めたのち、当地の群馬県藤岡市に勤務する文化財保護行政官でもある。そこで起こっていたことをひとつの学術的な物語として編み直す方法論を、東京大学大学院の文化資源学専攻で追究した成果が、2016年に同専攻に提出された博士論文を元に書かれた本書である。
序章、終章のほか、Ⅰ.「市民参加型発掘調査の系譜」(第1章〜第3章)、Ⅱ.「発掘調査における市民参加の転換」(第4章〜第8章)の二部構成。第Ⅰ部では、文化財保護に関わる制度の成立、アカデミックな考古学とアマチュア研究との交差など、日本の戦後発掘調査史が野尻湖発掘に至る前史として語られる。第Ⅱ部からは、1962年に始まる野尻湖発掘がどのような発展を辿り、いかにして社会教育の現場としての意義を獲得していったのかが示される。長期間に渡る様々なエピソードのなかで描かれるアクターは、相当に多様である。例えば、行政の文化財課、地質学や考古学を始めとした大学研究者、学会、市民研究会、中学校高校のクラブ活動、展覧会・博物館、友の会、さらには開発事業者、出版、百貨店やマスコミ…。
この渦の中では、アカデミアは研究総体の一つの歯車に見えてくる。むしろ、博物館が重要な役割を果たしていた。博物館建設に至るプロセスを通じて、様々な方向性に拡散していた、思想・運動、行政や観光事業、地域住民の生活や教育は、あるひとつの方向へと収斂することになる。すなわち、ミュージアムが調整のための場として機能し、結果、野尻湖発掘のコミュニティには「発掘調査を含めた学術研究への市民参加」という文化が醸成されることとなったのである。この事例からは、ミュージアムが、一般に理解されるようにコレクションを保持する場所であり、近年盛んに論じられるようにコミュニケーション/コラボレーションやネゴシエーションが行われる場でもあることに加え、さらに、コーディネーションの場でもあるという視座が示されている。
終章では、今日の文化財行政への提言がなされる。土屋氏の整理によれば、発掘調査は「専門性」、「調査の還元」、そして「行政システム」の三点で課題を抱えている。野尻湖発掘史からこれらを乗り越えるヒントが得られる。発掘調査を市民に開くことによって、異なる様々な研究分野や、非アカデミックな研究の担い手を取り込んでむしろ学術性を高めることができる。そして、調査から博物館展示、地域史の編纂、さらに長期的に見れば学術論文執筆まで行う人材をフィールドで育てることができる。すなわち、埋蔵文化財行政は社会教育の場として機能する。このようなアイディアである。現在求められている「専門家」とは、この開かれた状態を作り、うまく維持できる存在なのである。それは人々に知識を啓蒙するのでもなく、また、知識を一方的に搾取するのでもない、ファシリテーター役となって別の研究分野や非専門家と協働しながら〈知〉の生産を最大化する──「共に学ぶ」研究者である。こうしたありかたが、新たな専門家像として有効であり、発掘調査のフィールドワークはこのモデルを生み出す可能性を秘めているのだという。
本文で引用こそされていないものの、科学がいかに構成されるのかを分析するためのアクターを拡張することで「科学」それ自体の捉え方を更新した、アクターネットワークセオリー(ラトゥール)を想起した。土屋氏は、〈知〉の構成にかかわるアクターを思わず圧巻と口にしたくなるほどに捉えることに成功している。というよりも、数多ある科学研究が対象としてきた現場でも同程度のアクターが関わっているのであろうが、普通は研究として編み上げる際に仕方なくいくつか捨象していると理解するのが適切なのかもしれない。評者は自身の研究で、「ミュージアム」という場を核として周辺のアクターを捉える科学研究・芸術研究の方法を模索している。この関心からも、「発掘調査」を軸にして様々な対象を捉えることに成功した筆者のフォーカスの妙や、専門家に留まらない様々な主体によってなされる学術研究という行為のなかで「科学」という概念がいかに交差しているのかを鮮やかに描き出している点に固唾を吞んだ。
私たち学術の専門家たる研究者は、いかにして〈知〉を捉えることが可能なのか。「学術」や「専門家」の概念を問い直すことでこの問いに回答する試みとして本書を読んだ。「人々と共に学ぶ学問」や「ファシリテーターとしての専門家」といったモデルは、今日の研究者の一つのあり方だろう。筆者は本書における〈知〉の定義を、「科学ジャーナル共同体の知識」と「生活知」の対立(奈良・伊勢田)、及び、「家畜化された思考」と「野生の思考」(レヴィ゠ストロース)の対立を提示しながら両極を包括するものであるとしているが、ここに示されているように、筆者がイメージする理想的な「専門家」とは、これらの対立項のうちの前者に対応する知的生産のプロフェッショナルでもあり、その一方で、社会での包括的な〈知〉の実現をデザインする技術者でもあるのだろう。この視座から、本書は、科学知と生活知の相互作用によって〈知〉が構成される歴史を描いた新しい科学史として読むことができた。評者もまた、アカデミズムの科学を相対化することを念頭において、アメリカ文化人類学史におけるアマチュア学者の活動や、科学を用いて原理主義信仰に基づく真理を根拠づける運動について知の生産の観点から研究しており、関連して大変に勉強になった。日本の考古学史や地質学史においてもこのような非アカデミズムの影響力を歴史叙述に取り込もうとする試みがあることを知って興奮を覚えた。機会があれば、隣接する研究領域や海外の事例についても土屋氏のご意見を伺ってみたい。
考古学、文化財行政など様々な現場での豊富な経験を総動員した、アカデミズムに留まることなく分野・領域を横断する方法によってのみ、本書は成立しえたのではないだろうか。土屋氏が「本研究は社会教育論ではない。(…)それは最終的に文化の問題として捉え返す必要がある」(p. 19)と述べるように、本書には「文化論」であるという柱がある。筆者はその柱とした文化資源学を、「文化と社会の関係が制度化・体系化され、自明視される以前の段階にまで立ち戻り、根源的な意味を問い直すことを通じて」「現在と未来に向けてよりよい社会の実現を求める領域」と説明する。この比較的新しい、未だ外延が明確ではない学問分野の可能性を証明した一冊である。
(小森真樹)