インタビュー(1) ファッションの現場から 小野智海(ファッションデザイナー)
── 今回は表象文化論学会『REPRE』の特集で、現場で活躍されている方に「学会に期待すること」を伺うという趣旨でインタビューをお願いしました。小野さんはファッションデザイナーとしてご自身の「名前のないブランド」を展開されています。理論的、学問的なことにも深い関心をお持ちです。まず、これまでデザイナーとして自己形成してきた歩みを振り返りながら、その過程で学問、ないし「学会的なもの」とどのような接点があったかお伺いしたいと思います。
小野 高校を出て文化服飾学院に入学し、洋裁の技術を勉強しました。ファッションの勉強をしているなかで、制作する上で理論的なアプローチができないかと思い、東京藝術大学の美術学部芸術学科に進みました。美術には「美術理論」と呼ばれるものがありますが、ファッションにはファッション理論と言うものはあまり聞いたことがありませんでした。最初はイコノロジーのようなものをファッションに応用できないかとぼやっと考えていたのですが、西洋のギリシャ・ローマの神話やキリスト教の文脈があって成り立っているものなので、そのままファッションに応用することは難しいと思いました。その後は、フーコーやメルロ=ポンティなど乱読していましたね。
── 学部の卒業論文は何で書かれたのですか?
小野 メルロ=ポンティの「沈黙」と表現についてです。芸大の学生の頃は、服以外でも、油画科の友人数名と匿名のグループで、作品を作ったりもしていました。例えば、ギャラリーを真っ暗にしてサンプリングした大根を切る音を流すというような作品など、視覚を遮断したことで生まれてくるイメージとは何なのかといったことを考えていたと思います。「闇」や「無音」ということに興味がありました。それは、何も無いということではなく、メルロ=ポンティの「沈黙」あるいは「黙せるコギト」というものが身体をさすように、表現の生成の場としてあるのだと思います。
── 鷲田清一さんのものなどは読まれましたか?
小野 『モードの迷宮』や「現代思想の冒険者たち」シリーズの『メルロ=ポンティ』は読みましたが、当時はファッションへの関心の持ち方についてはそれほど影響を受けていないと思います。あとはバタイユやマラルメをよく読みました。マラルメの『骰子一擲』を読んだときは、自分がやりたいと思っていたことがもう100年以上前になされていたということに衝撃を受けました。先ほどの闇もそうかもしれないけど、その都度そこで何かが生成したり、もともとあるもののなかで別のものに変容していく構造というか、その可能性を内包する表現の形に驚かされました。そして、それは今の服作りにも影響していると思います。
── 卒業後は?
小野 フランスにあるオートクチュールの組合学校に編入しました。オートクチュールの仕立ての本当の技術に興味がありました。ただ、組合学校がデザインの方に寄っていこうとしていた時期で、意外にクチュールの授業が少なかったので、2年目の途中で3年生に上がって、1年で卒業しました。
── 留学中は理論というより、職人的手業に注力していた感じでしょうか?
小野 そうですね。日本を出る前に、理論的に考えることをいったんやめて肉体的に思考しようと思っていました。オートクチュールでは、タイユール(テイラー)とフルー(ドレス)といって、固い布を扱う技術と柔らかい布を扱う技術の部門が分かれています。日本では平面製図による教育のため──平面製図というのは19世紀中ごろ衣服制作への幾何学の応用として発展したものですが──、あるいはドレスを着る機会というのが少ないといった事情もあって、文化的にどちらかというとテイラーの方が強いので、フランスでフルーを学びたいと思っていました。柔らかい布というのは、水で形を作るかのように、マテリアルをコントロールするのが難しいのですが、ちょうど、パターンを作るモデリズムの先生がニナリッチのフルーにいらっしゃった方で、細かな襞を入れたビスチェを作ったときは、襞の影をすべて手縫いで留めつけたり、シルクサテンのドレスを作ったときは、大きくあいた背中の空きを背中のラインに沿わせるように、バイアスに切って伸ばしたサテンを微妙なテンションをかけながら留めつけて背中のラインに沿わせたりと、そういった細かいテクニックも学びました。
── 組合学校を卒業された後は?
小野 ルフラン・フェランとマルタン・マルジェラのコレクションラインでスタージュをしました。ルフラン・フェランは3ヶ月、マルタンは1年くらい。その後30歳で帰国して1年くらいして自分のブランドを始めました。この時期もそれほど踏み込んだ読書をしているわけではありませんが、鷲田さんの本だとか、ルドフスキー『みっともない身体』、デカン『流行の社会心理学』などは読んでますね。あと、仕立ての技術史的な本は読んでます。19世紀、20世紀初頭の資料を文化服装学院の図書館で集めたりしました。
── 帰国するまでにご自身のデザイナーとしての方法論を形成していく上で、影響を受けた人はいますか?
小野 影響という意味では様々な人に影響を受けていると思います。先ほどのマラルメや、芸大で教わった紫牟田和俊さんや彫刻家の川島清さんなど、どう影響を受けたのかを客観的に分析するのは難しいですが、私としては、彼らの作品を見ることは、どこか根底で制作の指標となっていると思います。また、影響というより対象として分析的に取り入れることはありますが、まったく無自覚なものもあります。例えば、コレクションでは、いつもどこかに赤い色を入れてしまうのですが、ある時ふと思い出して、それは20代のころに見ていたカミーユ=コローの絵の影響だと気づきました。その時は逆に、コローの色調でコレクションを作ることをしました。
── ファッションデザイナーでは?
小野 高校生の頃はKENZOに憧れていましたので、まずは高田賢三ですかね。KENZOのフォークロア調のデザインや美しい色彩の花柄など、その頃は熱狂的でしたね。今も好きですが、それが自分の服作りに表面的に現れるわけではないです。ボルヘスのエッセイの「ボルヘスと私」ではないですが、自分で作るものと、自分が好きなものは別な気がします(笑)。クチュール系だと、60年代のバレンシアガの現在でも色あせないデザイン。80年代のクリスチャン=ラクロアのスパニッシュな開放的な色彩、イヴ=サンローランのエレガンス。80~90年代のゴルチェのアヴァンギャルドなデザイン、90年代のマルジェラの越境性や衣服の可能性を追求する姿勢や、あるいは三宅一生の一枚布の考えなど。生き方としてはポール=ポワレも素敵ですね(笑)。
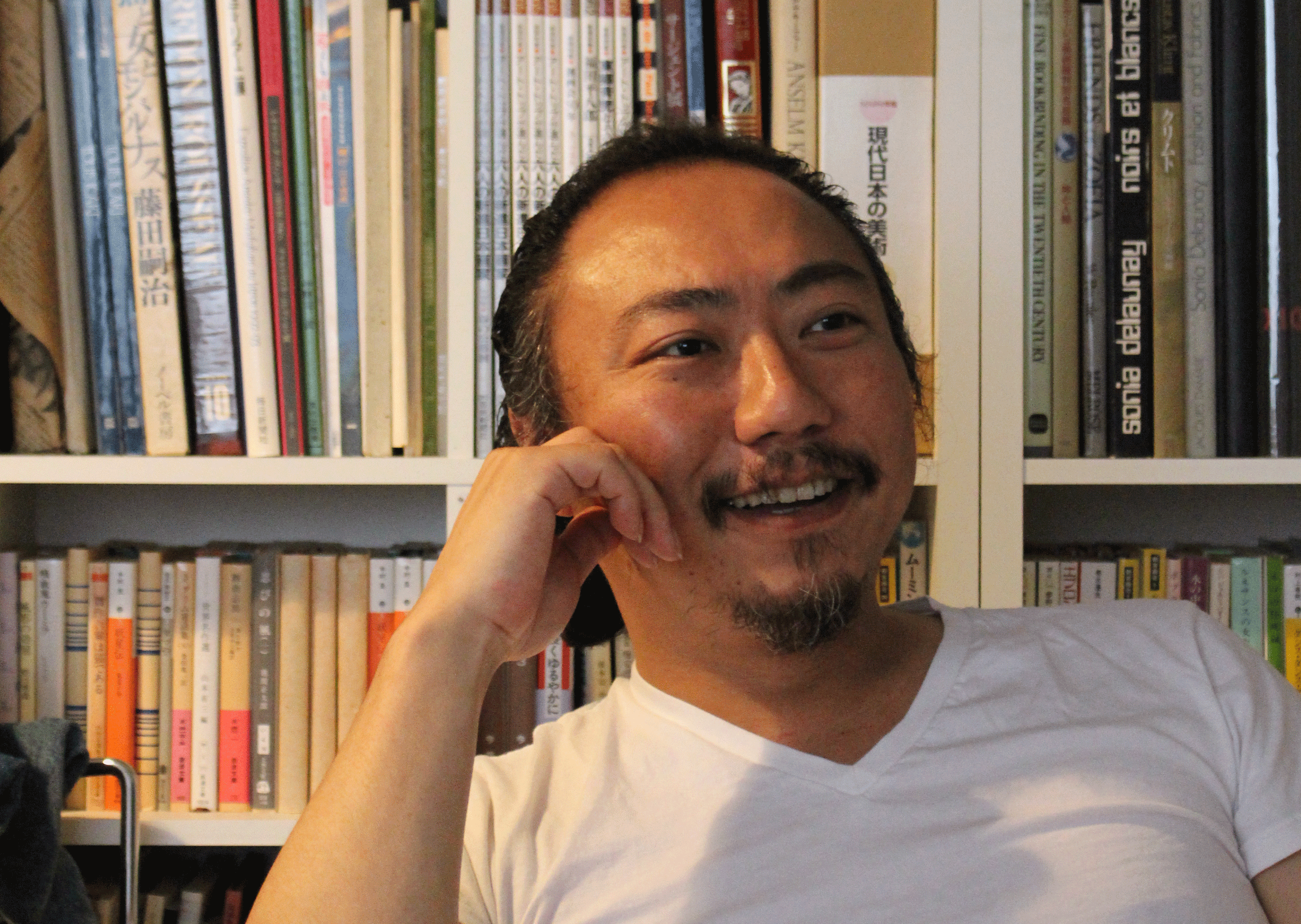
── では現在に至るお仕事について伺います。ブランドを始めた当初から「名前のないブランド」というコンセプトは決まっていたのでしょうか。
小野 そうですね。また、名前がないことによってどのように扱われていくのかということにも興味がありました。ブランドとして同定しにくく、検索をかけることもできないですし、一般的には非常に扱いづらいと思いますが、これは私自身ずっと興味を持っている事に繋がっていますので。
── 最初はどのようにして売り始めたのでしょうか?
小野 最初は何もわからない状態のまま展示会をして、調べのつくお店やバイヤーに片っ端からインビテーションを送るという感じでした。最初の展示会はZENSHIの岩本町のギャラリーでした。そして、最初のお客さんはメキシコ人の方でした(笑)。お店だと、パリで会った中目黒で古着店をしていた友人が最初に買い付けてくれました。そこから、買いつけてくれるショップで売るようになっていった感じです。
── お客さんは、セレクトショップでいろいろ見ているうちに、小野さんの服だと気付かないまま買っているかもしれないわけですね?あとからよくよく見てみると、買った服には同じタグがけっこう付いていたりして。
小野 それは素敵ですね。匿名になりながらも、完全に匿名ではない。確定した記号としてじゃなく、ある状態としてそこに存在しているというのが理想です。最近は存在しないことに興味がありますが、ブランド自体を否定しているわけではありませんので、服と出会う経験が、ブランド名という記号に収斂することなく、少しずつ動いて揺らいでいて欲しいと思っています。
── 小野さんの服であると承知で選んでくれることも、それはそれでかまわない?
小野 むしろ、着る人にとってのぼくの服に対するある種の共感をどう作れるか、ということは大切だと思います。共感は、もちろん服という物の持つ雰囲気や印象を通じてということもありますが、モノとしての服以外の部分でも作られるものですし、それらは切り離して考えることはできないと思います。コレクションであれば写真や動画、テクストといったものも、それは周縁的というより、ある意味等価に存在していていると思います。そして、選ばれた服が、あるいは着る人自身が、それらによって変化することができればと考えています。共感次第で、同じ服が、着る人によって、またその人の時間によって変わりうるものだと思います。
── これまでどういったメディアで発信されていますか?
小野 Webでは例えばChange FashionやFashionsnapにインタビューを載せて頂いています。雑誌では『主婦の友』や『ユリイカ』にも寄稿させていただいたこともあります。ブランドのサイトもありますが、ただ、それ以外のことができないかを今は考えています。ただメディアで発信するということではなく、極端な話、服でありながら服ではないものとして、表現することや発表することが、何かできないか、と。そういう点で、表象文化論のような学問の世界と接点を持ったり、研究者の人と一緒に場を作ったりできれば面白いと思っています。
── これまでに具体的に表象文化論学会やその他の学会に参加されたことはありますか?
小野 学会には入っていませんが、たまたま表象文化論の関係者だと、米田尚輝さん、福田貴成さん、平倉圭さんなど、友人や知人が多くいます。学生の頃は東京大学出版会が出した『表象のディスクール』は読んでいましたし、学会誌の『表象』などは読んだことがあります。友人の書いたものはできるだけ読むようにはしています。私自身の興味にかかわるものであれば、発表など聴きに行きたいと思っています。ジャンルは違いますが、せっかく彼らと一緒にいるので、知を共有ながら、何かできればと思っていますね。学術的な知の先端に触れることは、私自身とても刺激になりますから。
── ファッションに関する表象文化論的な本や文章に刺激を受けたことはありましたか?
小野 哲学や理論や他分野の研究には刺激を受けますが、それをファッションに応用したものとなると、それほど多くはありませんね。ファッションについての本で最近読んで面白かったのは、田中千代がずっと以前に書いた、『新女性の洋装』(1933)です。「洋服で空間を支配する」とか書いていたりするのですが、私自身は感覚としてそれがどういう状態か理解できず、面白かったですね。また、「清楚なお嬢さんであればこういう格好や色が合う」みたいな、ちょっとマーケティング的な分析も面白いなと思って読みました。それから和洋女子大の創始者堀越千代、山脇洋裁学院(現山脇美術専門学院)の山脇敏子など、明治から昭和にかけての、洋裁教育の成立や文化的な状況には興味があります。教育における平面製図と立体裁断の関係とか。デザイナーとしても、知的興味としても、身体を取り巻く服の空間を表象する技術の成り立ちを知りたいと思っています。
── 洋裁や教育法については、実証的な服飾史の分野で研究されているように思いますが。
小野 そうですね、技術的な話をすれば、例えば人の体に合わせてオーダーで作る際に、メンズは平面製図である程度捉えられますが、レディースはなかなかできない。なぜかというと、女性の胸があって、それを寸法から平面製図でどう処理するかということは、なかなか難しい。一つにはダーツの処理というのがありますが、同じ寸法であっても、実際にはどこに肉がついているのかで、パターンは異なります。バストの寸が80cmというとき、ぐるりと計った寸法は80cmかもしれませんが、実際には、胸が高くて80cmなのか、背中側に肉がついていて80cmなのか、バストを計っただけでは分からない。採寸方法には、短寸式と長寸式というのがあって、短寸式というのは、多くの箇所を採寸してそれを製図に反映させる方法で、長寸式というのはできる限り少ない採寸箇所で、それに応じた比率で製図する方法です。短寸式は採寸箇所が多いので体型を把握しやすいのですが、一方で採寸者の技量が求められる。長寸式は採寸箇所が少ないので比較的熟練しなくても採寸できますが、ただバスト等からの比率で製図するため実際には標準的な体型以外には合わない。もちろん、どちらの方法でも、実際に形を作って補正して合わせるわけですが、教育という点でいうと、文化服装学院などの原型の製図方法は、長寸式で、これは多くの人に同時に教育するのにやりやすい方法だったのだと思います。そういう、表面に出てこない、作り手は知っている知みたいなものがあると思います。
── そういった洋裁教育とも絡まる技術的な「知」の歴史が学問の対象になっていないということでしょうか。
小野 少なくとも、ファッションに関する批評なり論考で、もう少しいま言ったような技術的な点を、踏み込んだところまで理解したものを読んでみたいという気持ちはあります。哲学や理論を当てはめるというよりは、服から考えられる思想というものを紡ぎ出せるのであれば、それは極めて興味深いですね。
── なるほど。一方で、新しい理論から服について語るということは今後も続くでしょうし、それなりの役割もあるようにも思いますが。
小野 そうですね。当然それはあると思います。ですから、深い技術的な知識、あるいは技術のみでなくクリエーションの考え方や方法などは、こちらから提供して、理論的なことは研究者から提示してもらって、それぞれの専門の知を共有することで、お互いを触発するような場があれば面白いと思います。
── そういったアイディアを小野さんが披露するというようなことは、残念ながら今の「学会発表」の枠のなかでは難しいかもしれません。
小野 もちろん、学会はアカデミックな水準を守るべきだと思います。だから、「学会発表」とは別枠のカジュアルな場があればいいと思いますね。それ自体が学術の成果とか、ファッションの成果ではないかもしれませんが、そこでのトークがその後のそれぞれの成果に結びつくような。
── そういう場を維持する条件やインフラの問題もありますね。ひと昔前は、研究者も今ほど忙しくなく、人文系の出版も余裕があり、一般向けのファッション雑誌でも、学術的な色彩の強い批評が載ることがありました。
小野 インフラということでは、まさに学会がそのあたりを担ってくれたらと思います。それはそれとして、ファッション誌や一般誌に、学術的な内容を分かりやすく書いたものを載せていく必要は、今でもあると思います。確かに、書店で思想の専門書のコーナーへ行く人は多くはないかもしれませんが、実際には知的なものへの関心は多くの人にあると思います。村田明子さんが國分功一郎さんと蘆田裕史さんを招いたトーク*がありましたが、そういったものを雑誌に載せるとか。若い人が思わぬ出会いをするかもしれない。そういったファッション雑誌などのメディアに接続することのできる編集者などとの繋がりを作っていくことも重要だと思います。
*國分功一郎、蘆田裕史、村田明子「Fashion as Prodiaglity?──浪費としてのファッションは可能か?」2012年12月1日(土)@SIEBEN。村田明子氏のブランドMA déshabilléの2013年春夏コレクションのレセプションパーティーで行われたトークイベント。
── たしかに、かつての小野さんのようなファッションに興味がある若者が、マラルメを読んでみようと思えるようなチャンネルというか、「背伸び」の契機が希薄になってきている状況があると思います。
小野 20代の人が、ということですよね。一つには、情報過多になっているという問題なのかもしれません。情報が多すぎて、選択できない、選択しなくなっていくという。それは、知的なことだけではく、モノに関しても欲望が希薄になっているかもしれません。もう一つには、成熟の規範が80年代90年代を通じて変化していったということもあるかと思います。
── 大きな流行が消費を喚起することがなくなっていますよね?
小野 パリなどのモードが、2〜3年してマスまで届くといった「流行」はまだあると思いますが。これだけメディアが発達しながらもその動きが意外と遅いことは、興味深いことです。一方では速すぎる側面もある。ベンヤミンがパサージュ論の中で、モードの短サイクル化によって、価格は安価なものになり、それによって、生産と消費の双方が短サイクル化しながら変化するというようなことを指摘していると思いますが、H&MやZARAなどの短サイクルでの生産を可能にしたSPAによるファストファッションの現在の状況によく当てはまると思います。こうして高速で加えられる変化の刺激は、変化というよりもむしろ単調な刺激となってしまう。ちょうどニューロンに単調な刺激を加え続けると、反応が低下するように、反応が鈍くなるという状況はあると思います。
── そこに決定的な「新しさ」や、ときめき、身体の感覚が変わる、社会が変わる、といった盛り上がりがなくなっているのではないでしょうか。服飾科の学生も減少しています。
小野 それはそうですね。もちろん人口減少のせいもあるでしょうが、それだけじゃないですね。ファッションというのは、日常性と非日常性の間で、自己の感覚や世界との関わり方を変えるものだと思いますが、それはある種の夢というか、恋することに近いような時に熱狂を伴った高揚があると思います。本来自己は変化によってしか同一性を保つことができず、だからファッションの欲望は自己の変化に対する欲望としてあるのだと思いますが、先ほど言った情報の過多とその質の変化によって、ファッションへの享楽的な消費というものが弱まっているような気がします。身体感覚の希薄さと情報への疲労によって、欲望が、夢のような非日常性への飛躍だとか直接的な身体感覚だとかを伴わないものにシフトしているのかもしれない。そして、身体を伴った変化の少ない日常の服へと向かっていく。一方で、消費としてみれば、享楽的なファッションから、美容や健康といった肉体に対する配慮への消費が強まっていることは興味深いですね。
── ファッションに限らず、文学や美術の趣味においても、今の若い人たちは、享楽的というか、唯美主義やデカダンなものに惹かれなくなっている印象があります。
小野 デカダンというのは、個人的にはとても魅惑的な響きがありますね。不道徳な、あるいは享楽的で破滅的な要素、官能というのは、若さにおいて最も輝きをもつものだと思うんです。そして、モードの根底には精神における永遠の若さというものがあると思います。言い方をかえると、それはいかに情熱を持つか、危険を冒せるほどの情熱を持つかということだと思います。そして、それは根本的には感情の問題であり情動の問題だということです。文学や美術あるいは思想においても、その理解というのはその根底にある感情の理解なのだと思います。いかに概念的な作品であっても、それを作らなければなかった理由というか、それはある個人的な感情があると思います。服を作ることにおいても、まずこの感情をイメージの中でどうとらえるかということが重要だと思います。そして、それを物質的な形にしながらその距離を測るわけですが、さらに言えば、それは服だけではなく、服を取り巻くものによっても作られるわけです。そういう意味では、服を着ることはそれらすべてを含んだ感情的な行為なのだと思います。最近自分が服ではないものとしての服をいかに作るかということに関心があるのも、そのことと繋がっています。さっき言った「共感」をどう作るかということです。その背景には、現実のお店だけではなくインターネットの空間で服に出会うという今の状況があります。この状況は服の本質にとって極めて興味深い状況です。
── ちょっと前には普通であった、店頭でモノに一目惚れするような経験とは随分違いますね。
小野 そうですね。現実というものを考えた時、物質的ないわゆる「現実」の空間とインターネットの空間が混ざった中を私たちはすでに生きてしまっているのだと思います。それがリアリティを構成している。そして、そこでなにをすべきかを考えています。服についての記述やことば、写真、映像、つまり服のイメージをどう経験するか、そしてその感情をどう経験するのかが重要になってくると思います。
── 肉体と服のインターフェイスに非常にこだわっている小野さんがそれを言うのが面白いですね。
小野 ある人が服を着るときに、モノとしての服と、それにまつわる情報の全てを含めてその服を着ているので。そこは、今の時代大きいと感じています。話を戻しますと、だから表象文化論の研究をしている友人やアーティストの友人たちから刺激を受けたり、そのなかで言葉を見つけたりすることは、自分にとって大事なことだと思います。
── 最後に、本学会に期待することをあらためてお聞かせ下さい。
小野 学会という場において、アウトプットする研究の内容に関しては、アカデミックな基準のものは研究者としてもちろん重要だと思いますが、先ほど言ったようにファッションの雑誌やその他の媒体でもそれが広く読まれるようになれば、もう少し現場との距離、あるいは少しでも表象文化論に関心を持っている人との距離が縮むと思います。また、創造と制作の現場にフィードバックする知のあり方という点では、アーティストやデザイナーなど表現者と一緒になにかをする場が表象文化論学会のなかにあればいいなとは思います。表現者の参加のしやすさという点で言えば、例えば「学会の会員」のシステムでも、必ずしも学術的な発表を求めるわけではない会員のシステムなどがあってもよいと思います。また、会員でなくとも会員の発表やイベントや著作に関するインフォメーションを受け取れるなど、インフォメーションを多くの人に届けて、関心を触発する構造を作ってくださればと思います。それぞれが関わる文化の中で、それらの文化を先端的な知によって読み解かれたものに関心を持つ人は多くいると思いますし、ファッションで言えば、そういった学会の活動に触れることを通じて、若い人がファッションについて知的に考えることの楽しさに気付くきっかけになればいいと思います。
2017年5月28日
TOMOUMI ONOアトリエにて